米国株中心のブログではありますが、今回はちょっと外れて、投資対象としての中国を検証していきたいと思います。
中国は成長しているのか?その“質”を問う:製造業偏重・内需の限界・中所得国の罠
中国は、EVやAI分野で技術的には世界の先端を走り、「世界の工場」から「世界のテクノロジー拠点」へと脱皮しようとしているように見えます。
しかし、構造的な課題がいくつも噴出しており、表面的な成長だけを見て判断するのは危険です。
この記事では、製造業偏重がもたらす過剰投資の罠、eコマースの成長と内需の限界、そして今後の最大の壁となり得る「中所得国の罠」について掘り下げ、投資対象としての中国をどのように見極めるべきかを整理します。
製造業偏重がもたらす”過剰の罠”
• 地方政府がGDP成長と雇用創出を優先し、EV・太陽光・AIなどの分野に一斉に投資。
• 工場の乱立 → 過剰供給 → 価格下落 → 利益率の悪化。
• 中央政府は警鐘を鳴らしているが、現場は制御できていない。
• 投資と需要のバランスが崩れており、構造的な非効率が顕在化している。
FTによると、習近平自身が「なぜ皆同じ分野に集中するのか」と不満を述べたほどの状況。
(「China struggles to break its addiction to manufacturing(中国が“製造業中毒”から抜け出せない)」2025/07/29)
eコマースは進んでいても、内需の底力は弱い
• アリババ、JD、拼多多(PinDuoDuo:PDD)などが成功し、eコマース取引額は世界最大級。
• しかし消費の中心は都市部の中間層で、農村部や若年層には波及しない。
• 社会保障の未整備(医療・年金・教育)が貯蓄志向を助長し、消費を抑制。
• 家計消費の対GDP比は約38%(米国:68%、日本:50%超)と極めて低水準。
• 若年失業率は15〜20%に達し、「欲しくても買えない」層が拡大中。
そして最大の壁「中所得国の罠」とは
中国は現在、一人当たりGDPで約12,000〜13,000ドル。これは“中進国”と呼ばれる水準であり、ここから高所得国(G7水準)へのジャンプには大きな壁が存在します。
中所得国の罠とは:
賃金が上昇して「低コストの強み」が消える一方で、イノベーションや高付加価値産業に十分に移行できず、成長が停滞する現象。
中国におけるリスク要因:
• 高付加価値産業への移行がまだ限定的(外資依存、知財課題)。
• 民間の自由な創造活動が抑圧されやすい統制型制度。
• 米国や欧州とのデカップリングによる輸出先の縮小。
• 社会保障や再分配政策が遅れており、消費主導型経済に転換しきれない。
成長モデルを「量」から「質」に転換できなければ、人口規模だけでは豊かさは得られない。
投資家として押さえるべき視点
• 中国全体にまとめて投資するのではなく、セクター・企業の選別が不可欠。
• 世界市場で競争できるEV・バッテリー・AI企業(例:BYD、CATLなど)は投資妙味あり。
• 一方で、制度的リスク(政府介入、情報の不透明性)は依然として大きい。
• 中国は「世界一の製造力」と「消費の脆さ」という二面性を持つ市場であると認識すべき。
後記
無料相談で、自分の投資判断を見直してみませんか?
中国をはじめ、今後の世界の成長センターをどう捉え、どうリスクとリターンを組み合わせていくべきか。
あなたのポートフォリオに合わせて、プロの視点でアドバイスを提供しています。
👉 【無料個別相談のご案内はこちら】:
jack.amano@wealthmaster.jp
officeyy@wealthmaster.jp
👉 【投資メルマガへの登録はこちら】:「心穏やかなお金持ちになろう」メルマガ登録

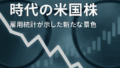
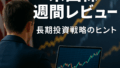
コメント